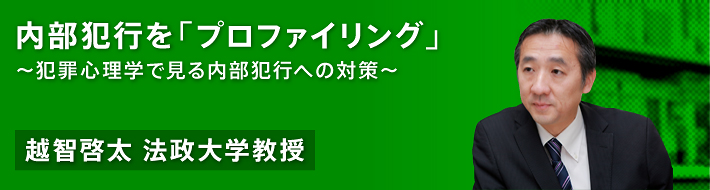
―「表出的」タイプが問題ということですが、犯罪が行われてしまう素地は何なのでしょうか?
越智氏:営業などの職種と違い、プログラミングなどの作業は、1人きりの作業でも仕事として成立します。大企業でも、部署の上司が細かいところまで把握していることはありません。
また、犯罪者が犯行するにあたって、自分の中で心理的負担を含んだコストとベネフィット(利益)を比較し、メリットが高ければ実行する「合理的選択理論」というものがあります。
PCを使った内部犯行では、犯行の際のコスト(負担)がありません。キーボードをたたいたり、マウスを動かしたりと、行為そのものは普段の業務でやっていることです。殺人をする場合、凶器を手にするまでの準備や、発覚の恐れ、犯行時の不快感などの心理的コストがあります。「振り込め詐欺」でも、いちいち電話を掛ける、という面倒(抵抗)がありますから。
 |
| 米国の金融業界と日本のIT業界 は似たような環境だったという |
越智氏:1990年代後半、金融商品が盛んに取引されていたころの米国では、金融業界が日本のIT業界と似たような環境になっていました。商品の運用者は複雑な金融商品を扱う能力があり、コミュニケーションができなくても仕事は成立する。当事者以外は何をしているのか分からない。
彼らは多くの情報を持っているケースがあるので、運用者が実力以上の給料を要求してくれば企業ものまざるを得ません。ですから金融商品を運用している社員の年収がうなぎ上りになっていったのです。
IT業界も金銭面で異なるだけで、技術を持っていて1人で仕事が成立する、部署の上司は詳しい業務まで分からない、という環境はほとんど一緒です。
―対策を取るのは難しいと思いますが、企業の「地雷」となってしまう「表出的犯行」の被害を最小限にするための方法はあるのでしょうか?
越智氏:曖昧なインセンティブを提示して人材を募集すると、企業が考えている以上に本人は期待を持ってしまうんです。その結果、入社したものの、本人は「期待とかけ離れた処遇を受けた」と思い、不満がたまる原因になります。
企業と従業員の契約関係をはっきりさせることが、犯罪の危険性がある従業員への対策になります。「表出的犯行」タイプの人間は、どのような環境にあっても、自分が理想とする立場にいないと不満を持ちますから、求人の段階で「ソフトウェア開発で○○をしたら○○万円の報酬」などのように記載して、入社後のギャップを少なくすることが必要だと思います。
権限を明確化し、やれることとやれないことをはっきりさせれば、恨みを抱いて「約束が違う」という話も出てこないはずです。高額な給料で契約社員にするなど、雇用形態を必要に応じて変えていくのもひとつの手です。
企業にとって「地雷」となってしまう従業員への対策は、とにかく契約関係をこれまで以上にはっきりさせ、「ビジネスライク」に接することです。少なくとも基準が明確でない成功報酬を掲げるよりも、効果があると思います。
上司のチェックが働かない個人の領域を作らない、といったことを含めて、組織の在り方へ根本的な手入れが必要になってきているのではないでしょうか。
 |
【越智啓太氏 プロフィール】おち けいた |
|---|
【関連カテゴリ】



注釈
*:科学捜査研究所(科捜研)
全国の都道府県警の刑事部に属する部署で、DNA鑑定、薬物の分析、心理鑑定などを行っている。科学警察研究所(科警研)は警察庁の管轄で、犯罪科学に関する総合的な研究機関。